モチベーションってなんだ?
- 小越 建典

- 2025年11月5日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月6日
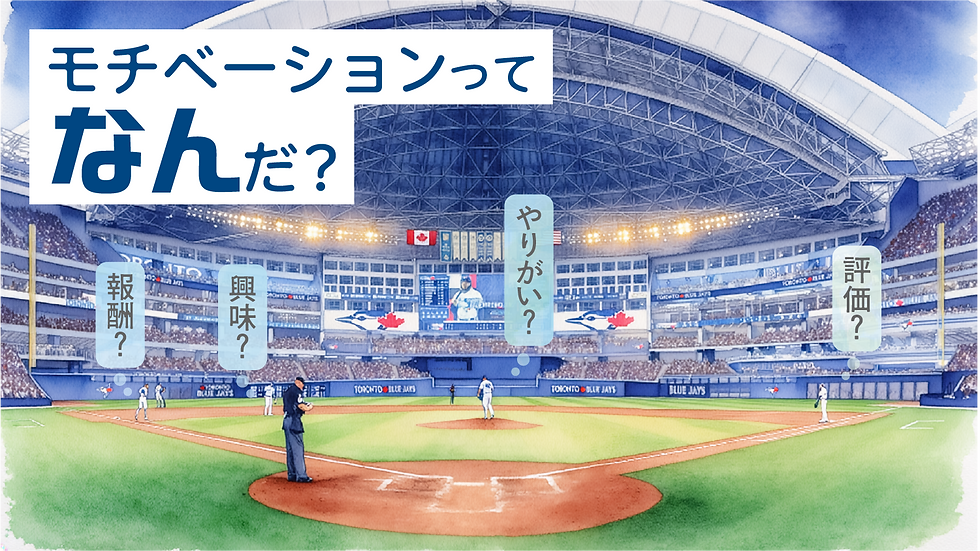
週末のMLBワールドシリーズは、圧巻の試合展開でしたね。特に前日先発したばかりでマウンドに上がり、劇的な逆転勝利にチームを導いた山本由伸選手の活躍には驚かされました。
グラウンドで戦った全選手に言えることですが、あのど根性はどこからくるのか?
私たちの仕事でも重要な「モチベーション」について考えてみました。
外発的動機づけと内発的動機づけ
よく持ち出されるのが、モチベーションには「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の2種類がある、という考え方です。外発的動機づけは、報酬や評価、罰則など外からの刺激で動くこと。内発的動機づけは、純粋に面白いとかやりがいを感じるとか、自分の内側から湧いてくる気持ちで動くことを指します。
どちらも必要ですが、内発的動機づけのほうが、本質的で長続きすると言われます。理屈としては、分かりやすいですね。
でも、あの試合で山本選手らが見せたど根性を、この二項で説明できるでしょうか。もちろん高額な契約という「外」の報酬はあるでしょう。野球が好きという「内」の情熱もあるはずです。でも、それだけであの気力というか、迫力の説明としては、足りない気がするんです。
環境と生産性は関係ない?
ここで興味深いのが、1920年代に行われた「ホーソン実験」です。この実験、最初は照明の明るさを変えたら作業効率が上がるか、という単純な問いから始まりました。つまり「環境を良くすれば生産性が高まるはず」という仮説を検証しようとしたわけです。
ところが結果は予想外でした。照明を明るくすれば作業効率は上がるのですが、不思議なことに、照明を暗くしても作業効率は上がったんです。これでは照明が原因とは言えません。そして、詳しく調べていくと、意外な事実が浮かび上がってきました。
作業者たちは実験に参加することで、観察者と頻繁にコミュニケーションを取るようになっていました。自分たちの意見を聞いてもらえる。注目されている。仲間と一緒に何かに参加している。そうした経験こそが、モチベーションを高め、生産性に影響していることがわかったのです。照明という「環境」ではなく、「人とのつながり」が本当の要因だったんですね。
大事なのは「内」「外」より「間」
この発見が示唆するのは、モチベーションを考えるとき、「外」か「内」かという二者択一ではなく、実は一番大切なのは「間」だということ。人と人との「間」、つながりの質こそが、モチベーションの核心にあるのではないでしょうか。
もちろん、外発的動機づけと内発的動機づけが、不要だという話ではありません。大切なのは、「間」を軸にして全体を設計することではないでしょうか。「外」も「内」も、人とのつながりを豊かにするための材料として捉え直すのです。
たとえば、外発的動機づけの報酬について考えてみます。確かに短期的には、報酬目当てに頑張れるかもしれませんが、孤立した努力は長くは続きません。一方で、チーム全体の成果に何かのインセンティブがあれば、仲間と助け合う関係が生まれます。報酬という外発的な要素が、つながりを強める方向につながります。
内発的動機づけについても同じです。自分の好きなことや得意なことに取り組むのは素晴らしいですが、それを一人で完結させてしまうと、行き詰まったときに続きません。誰かと進捗を共有する、教え合う、フィードバックをもらう。そうした「間」を意図的に作ることで、モチベーションは持続するのではないでしょうか。
ドジャースの選手(ブルージェイズも)は、自分というよりチームのために、戦っているように見えました。プロフェッショナルですから、報酬や評価も、野球への情熱も重要ですが、それだけでは限界を超える力は出ないのかもしれません。
てらすラボでは、GUTS×社長、GUTS×看護師など、お仕事の感動話を掲載しています。
もしまわりで感動話を知っている方、推薦をお願いします。
お問い合わせはこちらへ。



